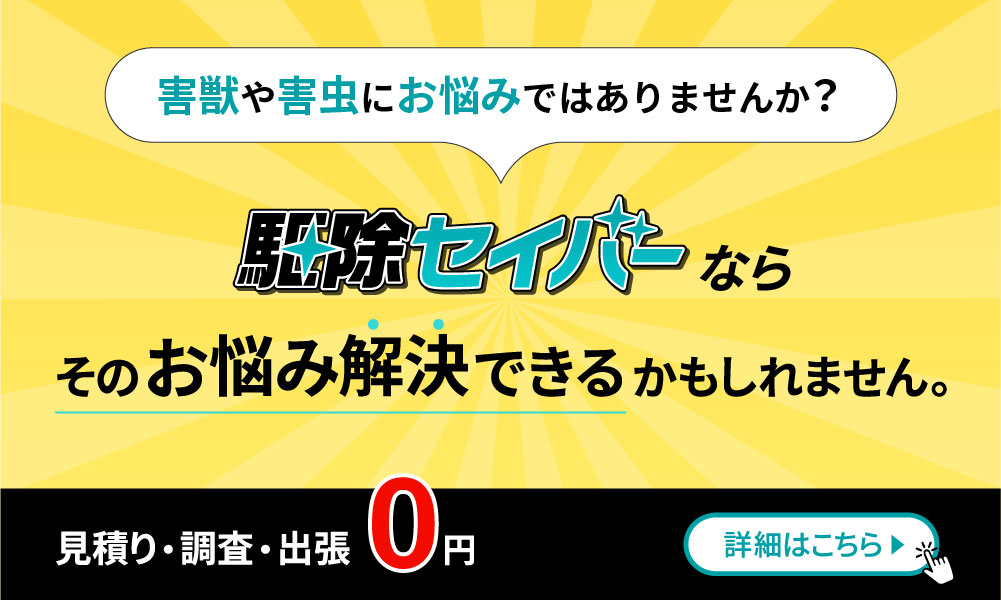コウモリが家に入ってきた!追い出す方法や侵入対策をプロが解説
2025.09.05
気づけば部屋にコウモリが――! 一見珍しい出来事のように思えますが、実際には戸建てやアパートなどで頻繁に発生しています。 ただ、慌てて追い出そうとしてもうまくいかないことが多く、対応を誤ると感染症や悪臭、さらには法令違反につながる恐れがあるため注意しましょう。 この記事では、プロの視点から「今すぐすべきこと」と「やってはいけないこと」を明確にし、追い出し・予防・再侵入防止まで、実践的な方法をわかりやすく解説しています。 「今すぐなんとかしたい」という方にも、「今後の被害を防ぎたい」という方にも役立つ内容です。 本気でコウモリ問題を解決したい方は、ぜひご参考ください。
CHECK
この記事を読むと以下のことがわかります。
- コウモリが家に入ってきたら今すぐすべきこと
- コウモリに対してやってはいけないこと
- 今後のコウモリの被害を防ぐための方法
部屋にコウモリが!今すぐ追い出す方法は?

部屋の中にコウモリが入り込んでしまったら、多くの人が驚き、パニックになってしまうかもしれません。
しかし、コウモリはむやみに刺激しなければ攻撃してくることはなく、落ち着いて正しく対処すれば、安全に追い出すことが可能です。
ここでは、部屋に入り込んだコウモリへの対処法として以下4点を確認していきましょう。
- 状況の整理
- やってはいけない行動
- 正しい追い出し方
- ライトで誘導して追い出すコツ
実践的な手順を具体的に解説します。
まずは落ち着いて状況を整理する
コウモリが部屋の中に入ってきた場合、何よりも大切なのは「慌てず、状況を冷静に把握すること」です。
パニックになると無理な対応をしてしまい、コウモリを興奮させて部屋中を飛び回らせてしまう原因になります。
まずは、以下を落ち着いて確認し、状況を整理しましょう。
- コウモリがどこにいるのか
- コウモリは飛んでいるのか
- コウモリは壁やカーテンにぶら下がっているのか
コウモリは光や音に敏感な夜行性動物で、慌てたり騒いだりすると混乱して飛び回るので気をつけましょう。
室内に入ってきたコウモリが1匹なのか複数なのかも把握しておくと、その後の対処がスムーズです。
また、侵入経路をできるだけ早く把握しておくことも大切です。
窓や換気扇、エアコンの配管まわりなど、どこから入ってきたのかを観察しておくことで、再侵入防止にもつながります。
まずは慌てず、静かに、そして正確に状況を見極めましょう。
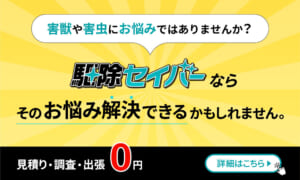
やってはいけないNG行動
コウモリを見つけた際に間違った対応をすると、健康被害や法的リスクを招くことがあります。
特に避けるべき行動は次のとおりです。
- 殺傷や捕獲する
- 素手で触れる
コウモリは鳥獣保護管理法によって保護されており、許可なく捕まえたり殺したりすることは違法です。
たとえ自宅内や駆除目的であっても、捕獲や殺傷が発覚すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、素手でコウモリに触れるのも危険です。
コウモリは病原菌やウイルス、ノミやダニなどの寄生虫を持っていることがあり、咬まれたり引っかかれたりすると感染のリスクがあります。
厚手の手袋をしていても完全に防げるわけではないため厄介です。
基本的には物理的な接触を避け、まずは安全な方法で追い出すことを優先してください。
これが基本!コウモリを傷つけず正しく追い出す手順

部屋に迷い込んだコウモリを追い出すには、「驚かせず、自然に外へ誘導する」ことが安全な方法です。
捕獲や駆除は鳥獣保護管理法に抵触するおそれがあるため、コウモリが自力で外へ出られる環境を整えましょう。
まずは室内の明かりを消し、窓やドアを1か所だけ大きく開けてください。
コウモリは夜行性のため、暗く静かな方向に向かって飛ぶ習性があります。そのやめ、外の光や風・空間の広がりを感じ取って自発的に出口へ向かうでしょう。
そのうえで、人は部屋の外に出て静かに待機してください。
バタバタと動き回ったり大声を出したりすると、コウモリが驚いて飛び回ったり、カーテンや家具の裏に身を隠してしまいます。静かに気配を消して見守ることが大切です。
また、市販の忌避スプレーやくん煙剤などもコウモリの追い出しには効果があります。
もし手元にあれば使ってみると良いでしょう。
<関連記事>
コウモリは自分で駆除できる?スプレーで追い出す方法など
ライトを使った効果的な追い出し方法
夜行性のコウモリは暗くて静かな場所を好む一方、強い光を嫌う性質があります。
そのため、光をうまく使えば、コウモリを出口へと誘導することが可能です。
やり方はシンプルです。
まず部屋の明かりをすべて消し、窓やドアなどの出口を開けておきます。
次に、懐中電灯やスマートフォンのライトでコウモリに光を当てます。
このとき、強く照らしたり急に近づけたりせず、距離を保ちながらゆっくりと照らしてください。
コウモリが光を避けて動き出したら、その動きに合わせて出口の方向へ誘導しましょう。
注意点は、光を当てる際に驚かせないことです。
強い光を近距離から突然当てると、パニックになって飛び回る恐れがあります。
特に、壁や天井に静止しているときは光への反応が出やすいため、そのタイミングを狙うと効果的です。
懐中電灯やスマホがあればすぐに実践できる追い出し方法なので、コウモリが逃げていける出入り口を確保し、光での追い出しを試してみてください。
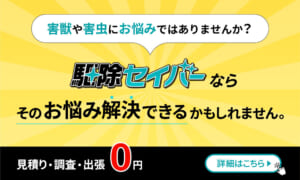
家に住み着いたコウモリの追い出し方法
屋根裏や換気口、エアコンの配管周辺などにコウモリが住み着いてしまうと、自然に出ていくことはほとんどありません。
むしろ繁殖が進み、悪臭や健康被害などの被害が拡大するおそれがあります。
特に、屋根裏・換気口・通気口などに定着してしまった場合、単に追い出すだけでは再び戻ってくることが多く、「追い出し」と「再侵入防止」の両立が不可欠です。
また、追い出しのタイミングにも注意が必要です。子育て中の時期(6月〜8月頃)に巣をいじってしまうと、幼獣だけが残ってしまい、死骸や悪臭の原因になります。
駆除の時期や方法を間違えると逆効果になることもあるため、状況に応じた対応が必要です。
ここでは、住み着いたコウモリへの正しい対処法として、
- 最適な駆除の時期
- 場所別の対策方法
- 効果的な対策グッズの紹介
といった具体的な対処手順を解説していきます。
コウモリの追い出しに最適な時期
コウモリの追い出しに最適な時期は、繁殖期を避けた「秋(9〜10月)」または「春先(4〜5月)」です。
注意すべきは、「夏(7月〜8月)」「冬(11月〜3月)」で、夏(7月〜8月)はコウモリの繁殖・子育て期にあたります。
この時期に追い出しをおこなうと、巣に幼獣だけが残ってしまうケースもあり、餓死や悪臭・害虫発生の原因になります。
場合によっては、幼獣を死なせてしまうことで「鳥獣保護管理法」に抵触する可能性もあります。
一方で冬(11月〜3月)は冬眠期のため、巣の存在に気づきにくく、コウモリ自身も動かないため追い出しが困難です。無理に刺激するとコウモリを傷つけてしまうリスクもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、コウモリが活発に動き、かつ繁殖や冬眠の影響がない「春」と「秋」が最適な時期です。
この時期なら、追い出しと再侵入防止の両方がスムーズにおこなえます。
場所・状況に合わせたコウモリの対策
コウモリは一度住み着くと、帰巣本能によって何度も同じ場所に戻ってくる習性があるため、追い出す+侵入経路の封鎖まで一貫しておこなうことが重要になります。
また、コウモリが長く滞在していた場所には、高確率で糞尿が蓄積しており、放置すれば悪臭やカビ、害虫の発生など、深刻な衛生トラブルにつながる恐れがあります。
そのため、清掃・消毒は必須の工程です。
ここでは、コウモリの侵入・滞在が特に多い3つの場所「天井裏・屋根裏」「換気口・通気口」「エアコン内部」に分けて、それぞれの状況に合った具体的な対策方法を解説します。
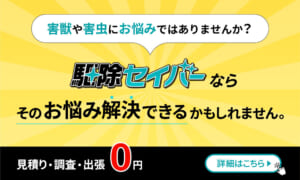
天井裏・屋根裏での追い出し対策
天井裏や屋根裏は、雨風を防げて暗く暖かく、エサとなる虫も豊富なため、コウモリにとって極めて快適な棲み処です。
わずか1cmのすき間からでも侵入できるため、知らぬ間に住み着かれるケースも少なくありません。
対策は空間の広さによって使い分けるのが良いでしょう。
屋根裏が広い場合
燻煙タイプの忌避剤を使うと効果的です。煙が広範囲に広がり、隅に隠れているコウモリも追い出せます。
屋根裏が狭い場合
ノズル付きの忌避スプレーをすき間に噴射する方法が適しています。薬剤が直接届けば、コウモリは強い刺激臭を嫌って自ら退去します。
ただし、忌避剤の効果は一時的なため、追い出しと同時に侵入経路の特定と封鎖作業をおこなうことが不可欠です。
再侵入を防ぐには、パテやシーリング材ですき間を塞ぐ必要があります。追い出したあとは再侵入を防ぐため、必ずすき間をパテなどで封鎖しましょう。
換気口や通気口に潜むコウモリへの対策
換気口や通気口は、建物外部と内部をつなぐ構造上、コウモリの侵入口となりやすい場所です。特に、古くなった換気カバーの破損や、防虫網の劣化・外れなどがあれば、1〜2cmのすき間からでも容易に侵入できます。
対策は、スプレータイプの忌避剤による追い出しです。
コウモリの嫌うハッカやミント系のにおいが含まれた製品を、換気口の内側から外に向けて噴射します。作業時はマスク・ゴーグル・手袋の着用を徹底し、コウモリに直接触れないように注意してください。
追い出し後は、侵入経路を物理的に封鎖します。換気を妨げないよう、11cm以下の網目を持つステンレス製の金網やパンチングメタルを使用し、すき間を物理的に遮断しましょう。
取り付けには、屋外使用に耐えうるビス止めや耐候性接着剤を用い、しっかりと固定してください。
なお、換気扇がついているタイプの通気口では、定期的に換気扇を作動させることでも侵入を抑止できます。
コウモリは音や風を嫌うため、換気扇の稼働が侵入防止に有効に働きます。
換気口は住宅全体の衛生環境に直結する箇所です。コウモリ対策は「追い出し」と「侵入防止」の両面から、抜け漏れなく実施する必要があります。
エアコン内部からの追い出し方法
エアコンの配管や室内機の内部は、外とつながるすき間が多く、コウモリが侵入しやすい場所です。特に室外機まわりのパテの劣化や、配管カバーのすき間は見落とされがちな侵入経路になります。
コウモリが入り込んでしまった場合は、むやみに叩いたり揺らしたりすると、内部の奥深くに逃げ込んでしまい、かえって追い出しにくくなることがあります。まずはエアコンの電源を切り、落ち着いて対応しましょう。
追い出しには、光や音といったコウモリが嫌がる刺激を活用します。たとえば、LEDライトで室内機の吹き出し口や配管周辺を照らす、超音波発生装置を近くに設置する、といった方法が効果的です。
強い刺激を与えすぎるとパニックを起こすおそれがあるため、ゆっくりと、距離を保って照射するのがポイントです。
忌避剤を使用する場合は、エアコンの故障の影響を防ぐため、スプレータイプは避け、燻煙タイプや置き型の忌避剤を選びましょう。
コウモリを追い出せたら、配管の引き込み口やパテの劣化箇所をチェックし、専用のパテや防虫キャップ、配管テープなどで再侵入を防止します。劣化したカバーはすき間が広がりやすいため、早めの交換が効果的です。
コウモリ追い出しに効果的な対策グッズ5選
コウモリを確実に追い出し、再び侵入されないためには、「効果のある対策グッズ」を正しく選ぶことが重要です。
中には効果が疑問視されるものや、使い方を誤ると逆効果になるものもあるため、根拠に基づいた選定が求められます。
特に、磁力を利用した忌避器具は科学的な裏付けに乏しく、実際の現場では効果が確認されていません。
一方、アブラコウモリが本能的に嫌う刺激は明確に知られており、以下のような要素が代表的です。
- ナフタレン(ナフタリンなどの防虫成分)
- ハッカやミントなどハーブ系の香り
- 煙やLEDなどの強い光
これらの性質を応用した対策グッズを活用することで、コウモリを傷つけることなく、効果的に追い出しと予防ができます。
このあとの「コウモリ追い出しに効果的な対策グッズ5選」では、こうした原理に基づいた実用性の高いおすすめアイテムを紹介します。
1. 忌避スプレー(きひスプレー)
忌避スプレーはコウモリが嫌うハッカやミントなどの香り成分を高濃度で含んだスプレーです。
狭い通気口や換気口、屋根裏のすき間に直接噴霧することで、一時的にそこから退避させる効果があります。
揮発性が高いため効果は短時間ですが、追い出し直後の封鎖作業と組み合わせることで非常に効果的です。
2. くん煙剤(くんえんざい)
屋根裏や天井裏など、広範囲への対処が必要な場合は、くん煙剤が適しています。煙が隅々まで行き渡るため、目視できない箇所に潜むコウモリにも有効です。
忌避成分を含む煙が空間全体に充満することで、コウモリを物理的に刺激せず、自然に追い出せます。
作業時には、火災報知器の停止や可燃物の管理など、安全面に配慮が不可欠です。
3. ジェル状忌避剤
ジェル状の忌避剤は、巣作りの抑制や再侵入防止に有効です。
粘着性のある薬剤に忌避成分が配合されており、コウモリの侵入ルートや滞在しやすい場所に塗布することで、長時間にわたり寄りつきにくい環境を維持できます。
屋外設置にも対応できる製品もあり、持続性を重視する現場で活用されています。
4. LEDライト
追い出し作業時の誘導手段としては、LEDライトの活用が効果を発揮します。コウモリは強い光を本能的に避けるため、閉じた空間から外に出したい場合に、照射による誘導が有効です。
特に夜間、部屋の明かりを落とした状態でライトを当てることで、コウモリがその反対側に逃げる性質を活用できます。
5. 超音波発生器
空間的な再侵入の抑止には超音波発生器が有効です。一定の周波数帯で断続的に音波を放つことで、コウモリがその環境に留まることを嫌がる状況が作り出せます。
特に通気口や軒下などに常時設置することで、新たな侵入を防ぐ補助的な装置として機能します。
これらの対策グッズは、それぞれ単独でも一定の効果を持ちますが、組み合わせて使用することでコウモリへの多面的な圧力となり、より確実な追い出しと再侵入防止につながります。現場の状況に応じて、効果的に活用してみましょう。
ご自分でコウモリ駆除をするのが不安な方は、コウモリ駆除業者に任せることを検討することをおすすめします。
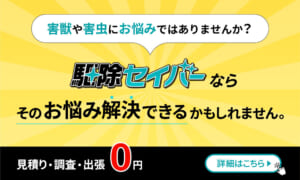
コウモリの侵入原因と寄せ付けないための予防対策
コウモリは、たまたま迷い込むのではなく、家の構造や環境がきっかけとなって入り込んでしまうことが多くあります。
特に、すき間が多い住宅や、エサとなる虫が集まりやすい場所は、コウモリにとって居心地のよい空間になりやすいです。
ここでは、コウモリが住まいに入り込む主な原因と、被害を繰り返さないための予防策について詳しく解説します。
日常的な点検や環境整備を意識することで、侵入を未然に防ぐことが可能です。
コウモリが家に侵入してくる3つの理由
コウモリが住宅に侵入してくるのには、偶発的な理由だけでなく、いくつかの目的があります。特に以下の3点が主な動機として挙げられます。
- 住処やねぐら・巣作りのため
- 冬眠場所を確保するため
- エサとなる昆虫を求めて近づくため
これらはいずれも、住宅の構造や周辺環境によって引き寄せられる傾向が強く、侵入を許す原因となります。
1. 住処やねぐら、巣作りのため
コウモリは雨や風、天敵から身が守れる静かな場所を好みます。屋根裏や換気口などは外敵が入り込みにくく、雨風の影響を受けにくいため、格好の隠れ家となります。
特に住宅の屋根裏は、木材や断熱材で構成されているため、コウモリにとって住処やねぐら・巣を作るのに最適な環境です。
2. 冬眠場所の確保のため
コウモリは夜行性のため、日光が届かず、断熱材の効果で比較的温かい屋根裏や天井裏を好みます。
特に冬場でも断熱性能の高い住宅では、外気温の影響を受けにくいため、越冬場所として選ばれやすくなります。
3. エサとなる昆虫を求めて近づくため
コウモリは主に昆虫を捕食する動物で夜行性です。そのため、住宅の外灯や植栽に集まりやすい「蚊・ガ・ユスリカ」などを求めて家の周囲に飛来します。
その過程で、ちょうどいいすき間(換気口・屋根瓦の間・通気口など)を見つけると、そこから屋根裏などに侵入するケースがあります。
以上のように、住宅にコウモリが侵入する背景には、いくつかの目的があります。すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、こうした傾向を踏まえたうえで対策を講じることが、被害防止につながります。
コウモリに好かれやすい家の特徴と予防対策
コウモリが住宅に棲み着くかどうかは、建物構造・周辺環境・管理状況に大きく左右されます。
特に以下のような条件を備えた家は、コウモリにとって安全で快適な住処となりやすいため注意が必要です。
- 外壁や屋根にすき間・劣化箇所が多い家
- 屋根裏・天井裏が暗く静かで暖かい家
- 周辺にエサとなる昆虫が多い環境
- 人の気配、物音や光の影響が少ない家
- コウモリが住み着いた家
コウモリは、「入り込めるすき間があり」「静かで暖かく」「エサが豊富」な場所に集まります。
屋根や外壁に1cm程度のすき間がある家、屋根裏が断熱性に優れていて暗く静かな環境、そして近隣に川や草木があって虫が多い場所は特に注意しましょう。
対策としては、すき間の封鎖、屋根裏に人の気配や光を感じさせる工夫、害虫対策、そして侵入後の清掃や消毒の徹底が重要です。
環境全体をコウモリにとって「居心地の悪い空間」に変えることが、最も有効な予防策ですね。
コウモリの追い出しで最も重要!再侵入防止策
コウモリを無事に追い出せても、そこで対策を終えてしまうのは危険です。というのも、コウモリには「帰巣本能」があり、一度住み着いた場所には再び戻ってくる習性があります。
再侵入を防ぐためには、「戻らせない環境」を確実に整える必要があります。特に重要なのが、コウモリの糞や尿による衛生被害を防ぐための清掃・消毒、そして侵入経路を確実に封鎖する物理的対策です。
ここでは、コウモリの糞による衛生被害を防ぐための清掃・消毒の方法と、侵入口を完全に封鎖する具体的な対策について解説します。
フンの清掃と消毒の徹底対策
コウモリのフンや尿は、におい成分にフェロモンや個体特有の化学物質が含まれており、これが再侵入の原因となります。
コウモリは帰巣本能が非常に強く、自分や群れのにおいを頼りにかつての住処へ戻ろうとするため、フンや尿を放置すると「ここはまだ安全な場所」と認識されてしまいます。
さらにフンの蓄積は、ダニ・ノミ・カビ・細菌の温床となり、住環境の衛生レベルを著しく下げる要因にもなります。呼吸器系への影響や皮膚疾患の原因になることもあり、放置は必ず避けなければなりません。
清掃ではまず、フンを確実に除去することが基本です。コウモリのフンについてもっと知りたい方は、この記事をご参考ください。
<関連記事>
コウモリのフン害は市役所に相談できる?生態や病気も解説
結果として、におい・病原体・誘因物質をすべて除去することが再侵入のリスクを大幅に下げることにつながります。
清掃や消毒は「衛生対策」と「再侵入防止策」という2つの重要な目的を果たすため、追い出し後は必ず徹底しておこないましょう。
コウモリの侵入経路を完全に塞ぐ方法
コウモリ対策で最も効果が高いのは、「侵入経路を徹底的に塞ぐこと」です。ただ追い出しただけでは再発を防げません。
1〜2cmのすき間でも自由に出入りできるため、目視では見落としがちな箇所まで丁寧に対処する必要があります。
そのためには、建物全体を点検し、屋根まわり・軒下・外壁・換気口・通気口などの潜在的な侵入口をひとつ残らず見つけ出し、それぞれに適した方法で封鎖することが重要です。
封鎖の方法は大きく分けて2つありまして、以下で詳しく説明します。
パテやシーリング材を使った隙間の封鎖対策
屋根材の継ぎ目、サッシまわり、外壁のひび割れなど、コウモリが通れるような1cm以上のすき間は、封鎖が必要です。このような箇所には「防水性」「耐候性」「密着性」に優れたパテやコーキング剤を使用しましょう。
外壁用としてはウレタン系やシリコン系のシーリング材がおすすめで、ひび割れやすき間に深く充填することで、長期間にわたりコウモリの侵入を防止できます。また、外装用パテは乾燥後に硬化するため、コウモリの爪や歯でも突破されにくくなります。
なお、施工前にすき間内部のホコリや油分を除去することで密着性が高まり、劣化もしづらくなります。雨水の侵入も防げるため、住宅の保全にもつながるためオススメです。
換気口や通気口には金網や防鳥ネットを活用
換気口や通気口は通気性を確保しながらも、コウモリの侵入を許さない構造にする必要があります。ここでは「パンチングメタル」「ステンレス製金網」「防鳥ネット」などの資材を使い、外側からカバーするのが一般的です。
特におすすめなのが、目の細かい(10mm以下)ステンレス金網です。
耐久性があり、コウモリでも噛み破ることができません。また、網目が細かすぎると通気性に影響するため、適度なバランスが重要です。
固定には結束バンドやビス、金具などを使用し、風や動物によって外れないように強固に設置しましょう。
場所によっては防虫ネットと併用することで、コウモリだけでなく虫の侵入も防げます。
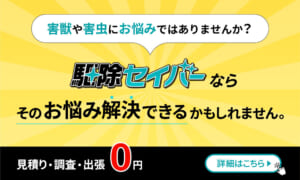
コウモリの追い出しと対策で知っておくべき重要注意点
コウモリの追い出しを自己判断でおこなう際には、法律や安全面に十分注意しなければなりません。
軽い気持ちで捕まえたり、追い立てたりすることで法令違反となる可能性があります。
また、健康被害につながる恐れもあるため、最低限押さえておくべき重要な注意点を解説します。
許可なく捕獲や殺傷はNG
コウモリは「鳥獣保護管理法(旧・鳥獣保護法)」によって保護されているため、許可なしに捕獲・殺傷することは禁止されています。
違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるため注意しましょう。
たとえば、自宅に侵入してきたコウモリを素手で捕まえたり、棒で追い払おうとして怪我を負わせる行為も「傷つけた」と見なされる可能性があります。
あくまで「追い出す」ことに徹し、物理的に接触しない方法をおすすめします。
なお、捕獲や駆除をおこなう場合には、都道府県の担当窓口からの許可が必要になります。
一般家庭で対応は難しいので、コウモリ駆除に精通した専門業者に依頼するのが最も安全で確実でしょう。
追い出し作業の安全対策と正しい服装
コウモリが自ら人を襲うことはほとんどありませんが、防衛本能で咬みつくことがあり、感染症のリスクが発生します。
また、体内やフンには細菌・ウイルス・寄生虫が含まれていることも多く、衛生面での対策は不可欠です。
追い出し作業をおこなう際は、感染症やアレルギーの予防のためにも、以下のような装備を必ず着用してください。
- 厚手の作業用手袋
- マスク(可能であれば防塵マスク)
- ゴーグルまたは保護メガネ
- 長袖・長ズボンの作業服(肌の露出を避ける)
さらに、フンや尿が落ちている場所ではビニールシートを敷く、作業後に靴底を消毒するなど、周囲への配慮も重要です。
屋根裏や換気口まわりなど高所での作業が必要な場合は、脚立や足場の安定性を事前にしっかり確認してください。
少しでも不安がある場合や、作業環境に不安が残る場合は、無理をせず専門業者に相談するのが賢明です。
コウモリ駆除をプロに依頼すべき3つの理由
コウモリの駆除を自力でおこなうのは、見た目以上に難しく、思わぬトラブルを招くことがあります。
プロに依頼すべき理由は大きく分けて3つあります。
- 法令違反のリスクを回避できる
- 衛生・安全面での被害を防げる
- 再侵入を確実に防止できる
この3点を押さえることで、コウモリ被害の再発を防ぎ、安心した生活環境を取り戻せます。
1.法令違反のリスクを回避できる
コウモリは「鳥獣保護管理法」で保護されている野生動物です。許可なく捕獲・殺傷すると、たとえ自宅内であっても法令違反に問われる可能性があります。
プロの業者はこの法律に精通しており、必要な手続きや許可申請を適切におこなったうえで作業します。
自己判断で違法行為に踏み込んでしまうリスクを避けるためにも、専門知識のある業者の関与は不可欠です。
2.衛生・安全面での被害を防げる
コウモリの体や糞尿には、細菌・ウイルス・寄生虫が含まれていることがあり、感染症やアレルギーのリスクがあります。
また、追い出しや清掃には高所作業が伴うこともあり、個人で対応するのは非常に危険です。
業者は専用の装備や薬剤を用いて、感染対策や安全管理を徹底しながら作業をおこなうため、二次被害を防止できます。
3.再侵入を防止できる
コウモリは帰巣本能が強く、一度住み着いた場所には何度でも戻ろうとします。
プロの業者は、侵入口の特定から封鎖処理、再侵入対策までを一貫して対応できるため、再発のリスクを根本から絶つことが可能です。
市販のグッズや自己流の封鎖では侵入口を完全にふさぐことは難しいですが、業者による専門的な施工なら確実性が違います。
コウモリが追い出せない時は【駆除セイバー】にご相談ください!
「何度追い出しても戻ってくる」
「自分ではどこにいるのかもわからない」
「触るのも怖いし、法律が心配」
このようにコウモリの被害で悩んでいる方は少なくありません。
一人で抱え込むと、衛生面や法的リスクが広がるだけでなく、精神的なストレスも大きくなります。
そのようなときは、無理せず【駆除セイバー】にご相談ください。
「いま動かないとまずいかも」
そう思ったときが、対処のタイミングです。どうぞお気軽にご相談ください。