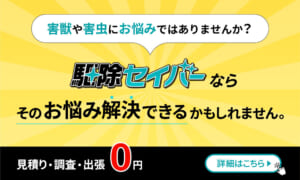ネズミ対策を徹底解説!自分でできる正しい駆除方法とは
2025.11.17
天井裏から聞こえる「カリカリ…」という音、食べ物の袋に残るかじり跡。 それは、すでにネズミが家の中で活動しているサインかもしれません。 ネズミの被害は放置するとあっという間に拡大し、配線トラブルや食品汚染など、健康面・衛生面・安全面すべてに深刻な影響を及ぼします。 「市販のグッズを使っても効果がない」 「何度駆除してもまた現れる」 そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、ネズミ駆除のプロである【駆除セイバー】が、正しいネズミ対策の手順を初めての方でもわかりやすくステップ形式で解説します。 被害を最小限に抑えるための考え方から、プロに頼むべき判断基準まで詳細にお伝えしますので、 「もうネズミに悩まされたくない!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
CHECK
この記事を読むと以下のことがわかります。
- プロが実践する正しいネズミ対策の手順
- ネズミ対策が失敗し、再発を繰り返してしまう理由
- 信頼できるネズミ駆除業者の選び方
ネズミ対策が急務である理由

ネズミの気配を感じたら、すぐにネズミ対策を始めましょう。
「少し物音がするだけだから」と放っておく、この油断が取り返しのつかない被害を招くことがあります。
ネズミは非常に警戒心が強く、夜行性で繁殖力も驚異的。
ネズミはわずか1匹でも数か月で十数匹に増え、気づいたときには群れができていることも珍しくありません。
ネズミの被害は衛生・安全・経済的損失のすべてに関わるため、「見つけたらすぐに動く」ことが何より重要です。
ここでは、なぜ早期の対策が欠かせないのかを具体的に解説します。
放置するとより深刻な状況になる

ネズミは夜行性で、人の気配がない時間帯に活動します。そのため、実際に姿を見かけたときにはすでに巣が完成しているケースが多いです。
繁殖スピードも非常に早く、1匹のメスが1年で60匹前後を産むこともあります。まさに「放置=被害の爆発」といっても過言ではありません。
そんなネズミを放置すると、次のような深刻なリスクが発生します。
| 被害項目 | 内容 |
| 配線がかじられることによる火災リスク | 電気コードをかじってショートし、火災へ発展。 |
| 食品汚染・廃棄ロス | 糞尿や毛・病原菌などが混入して食品が使えなくなる。特に飲食店は営業停止の恐れあり。 |
| 建材・家具の破損 | 断熱材や木材がかじられ、修繕費用が膨らむ。 |
| ダニ・ノミなど衛生害虫の発生 | ネズミに寄生する虫が人間にも被害を及ぼす。 |
| 悪臭・騒音問題 | 糞尿や死骸、夜間の走り回る音が生活環境を悪化させる。 |
ネズミの被害は「いつの間にか広がる」ものです。
ネズミ対策の初動が遅れるほど、封鎖すべき穴の数・清掃範囲・工期が増え、結果的に費用も大幅に上昇します。恐ろしいですね。
健康被害や火災リスクを考えれば早急なネズミ対策が必要です。「ネズミがいるかも…」と思った時点で、すでに家の中で繁殖が始まっている可能性があるため気を付けましょう。
すぐに調査と対策を始めることが、被害を最小限に抑える唯一の方法です。
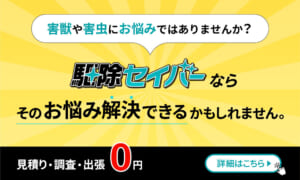
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970
被害を最小限に留めるため、ネズミ対策は不可欠
一方で、注意しなければならないのが、誤った順序で対策をおこなってしまうケースです。
たとえば、闇雲に殺鼠剤をまくと、死骸が見つからず悪臭が発生したり、生き残った個体が薬剤の危険を学習して避けるようになったりします。
また、ネズミを追い出す前に穴を封鎖してしまうと、逃げ場を失った個体が屋内で繁殖し、かえって被害が拡大してしまうこともあるため要注意。
正しい手順を守らなければ、状況を悪化させる結果につながりかねません。
ネズミ対策を効果的におこなうには、事前の調査と準備の徹底と、駆除と侵入経路封鎖の同時対策が大切です。
ネズミ対策後は、捕獲数の推移やラットサインの消失、夜間の物音がなくなるなど、具体的な変化を確認し、「問題を一時的に収める」のではなく「再発そのものを防ぐ」ことを目指して対策を継続しましょう。
プロが教える、正しいネズミ対策

ネズミ対策で最も重要なのは「順番」と「正確さ」です。
闇雲に忌避剤や殺鼠剤を使っても、根本的な解決にはつながりません。
プロのネズミ駆除では、被害の原因を突き止めてから、ネズミの行動に沿った手順で対策を進めるのが基本です。
ここでは、現場で実際におこなわれている「再発しないための正しい手順」を、一般家庭でも実践できるレベルに落とし込んで解説します。
まずは、すべての対策の基礎となる「STEP0:事前準備」から始めましょう。
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970
STEP0:ネズミ対策前の準備と調査
ネズミ対策を成功させる第一歩は、敵を正しく知ることです。
どんな種類のネズミが、どこから、どのように出入りしているのか。
これを把握しないまま対策を始めると、的外れな方法に時間とコストを浪費してしまいます。
STEP0では、主に以下の2つをおこないます。
- 家にいるネズミの種類を特定する
- ラットサイン(痕跡)から侵入経路を推測する
<<参考記事>>
ネズミ被害にご注意を!放置することで起こる危険とは
家にいるネズミの種類を特定する
ネズミといっても、家庭や店舗に現れるのは主に「クマネズミ」「ドブネズミ」「ハツカネズミ」の3種類です。
それぞれの生態や行動範囲が異なるため、種類の特定をすることで効果的なネズミ対策がしやすくなります。
| 種類 | 特徴 | 好む環境 | 行動範囲 |
| クマネズミ | 細身で尾が長く、運動能力が高い。 | 屋根裏・天井・高所 | 建物上部中心に活動 |
| ドブネズミ | 体が大きく、水辺や下水を好む。 | 床下・配管周り・湿気のある場所 | 地面や排水管沿いに行動 |
| ハツカネズミ | 小型で繁殖力が非常に高い。 | 倉庫・納戸・食品庫 | 限られた範囲で巣を作る |
こうした違いを見極めるには、糞の大きさや形、足跡の位置、かじり跡の高さなどを観察するのがポイントです。
天井裏の音が聞こえるならクマネズミの可能性が高く、床下や配管周りの痕跡が多ければドブネズミを疑いましょう。
スマートフォンで糞や足跡の写真を撮っておくのもおすすめです。あとからネズミ対策の専門業者に相談するとき、これが重要な手がかりになります。
ラットサインを辿って侵入経路を推測する
ネズミの種類を特定したら、次はどこから侵入しているのかを突き止めましょう。
ネズミは決まった通路を何度も通る習性があり、その通り道には必ず痕跡(ラットサイン)が残ります。これを辿れば、出入り口や巣の場所を高い確率で特定できます。
主なラットサインは「黒いこすり跡」「糞」「かじり痕・足跡・尿臭」です。
次のようなラットサインを発見したら、発生位置と数をメモや写真で記録しておきましょう。
| ラットサイン | 説明 |
| ラビング痕 | 壁や配管に残る黒ずみ(体毛の油分による擦れ跡) |
| 糞の帯状配置 | 小粒の黒色で乾燥した糞が、一定間隔で連なり落ちている |
| かじり痕・足跡 | 木材・配線・袋などに鋭い歯型 |
| 足跡 | 壁際や床に4本指の前足と5本指の後足の跡が並ぶ |
| 尿臭 | アンモニアのような強い臭いが漂うことがあり、糞と同時に見つかることが多い |
重点的に調べる箇所は、建物の外周の基礎や排水管、配管の貫通部。さらに、屋根や換気口周りもネズミの通り道になりやすいので確認します。
室内では、壁際・天井裏・キッチン周辺を中心にチェックしましょう。
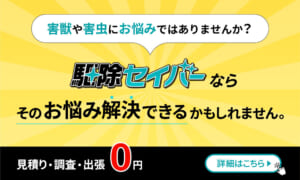
STEP1:まずは家から追い出す
ネズミ対策の第一段階は、「家の中からネズミを追い出す」ことです。多くの方がいきなり殺鼠剤を使ってしまいますが、これは誤り。
まだ侵入経路を把握していない段階で薬剤を使うと、屋内の奥へ逃げ込んだり、死骸が残って悪臭を放つなど、かえってネズミ対策を難しくしてしまうことがあります。
ここでは、プロも実践する「安全かつ効果的にネズミを家の外へ追い出す」ための対策方法を紹介します。
くん煙剤やスプレーの効果的な使い方と注意点
くん煙剤やスプレータイプの忌避剤は、ネズミを一時的に退避させる補助的な対策手段として有効です。
ただし、あくまで「追い出し」のための手段であり、根絶策ではありません。
使用する際は、部屋を密閉してから噴射し、一定時間放置します。このとき、在室者やペットは必ず外へ出しましょう。
使用後はしっかり換気し、火災報知器がある部屋では誤作動を防ぐためカバーをかけておくと安心です。
ネズミの数が多い現場では、刺激によって別の部屋や壁内へ逃げ込む可能性があるので注意が必要です。
ネズミが本能的に嫌がる匂いを活用する
ネズミは嗅覚が非常に発達しており、次のような匂いを強く嫌う性質があります。これを利用すれば、巣や通路に近づきにくくさせることが可能です。
- ハッカ油・ミント・ユーカリなどの精油系
- 木酢液やクレゾール(殺菌・防臭効果も)
- 唐辛子成分(カプサイシン)
これらを通路や潜伏しやすい場所の手前に配置することで、活動範囲を狭められます。
しかし時間が経つと匂いが薄れ、ネズミが慣れてしまう「馴化」も起こるため、匂い単体での完全対策は難しいです。
そのため、1〜2週間おきに再塗布しながら、STEP2・STEP3の物理的対策と組み合わせて使ってみるといいでしょう。
超音波装置は本当に効く?
最近注目されているのが、ネズミが嫌う高周波を発する「超音波装置」です。確かに一定の効果はありますが、設置条件を満たさなければ効果は限定的です。
音波は家具や壁で反射・吸収されるため、設置位置が悪いと効果が出にくくなります。
部屋の角や通路に向けて角度を調整し、複数台を組み合わせることでようやく効果が安定します。
ただし、長期間使うとネズミが音に慣れる場合もあります。
そのため、「音で不快にさせる」→「追い出し・侵入経路封鎖で急いで対策」というスピード感ある流れを意識することが大切です。
実際に導入する際は、設置前後のラットサインを記録して効果を比較すると、装置の効き具合が客観的に確認できます。
STEP2:潜んでいるネズミを捕獲する

ネズミ対策として追い出しをおこなった後も、家のどこかにネズミが残っている可能性があります。
ここで大切なのは、逃げ場を作らずに確実に捕まえることです。
この段階では「粘着シート」と「殺鼠剤」をうまく組み合わせ、家の中に残った個体を一掃していきます。
粘着シートの適切な設置場所
最も基本的で効果的な捕獲方法が、粘着シートを使ったトラップです。
ただし、ただ置くだけでは効果が半減するため、設置場所と枚数の考え方が重要になります。
ネズミは壁沿いを移動する習性があるため、まずは壁際や通路沿いに連続して敷くのが基本。
一枚おきに隙間をあけるのではなく、シート同士を橋渡しのようにつなげて連続して配置することで、ネズミが通過する際に捕獲できる確率が上がるでしょう。
部屋の角やドアの開口部前など、通り道が絞られる場所にも重点的に設置することをお勧めします。
粘着シートの適切な枚数
シートの枚数は「広さ」ではなく「通路の数」と「活動量」で決めます。
使用する際は、1枚や2枚ではなく、通路を覆うように広範囲・多枚数で配置するのが効果的です。
捕獲率をさらに高めたい場合は、設置前に次のような工夫をおこないましょう。
- 粉(小麦粉など)をまいて、ネズミの通路を確認してから配置する
- 前日に「粘着なしのシート」を置いてネズミを慣らす
- 手袋をつけて人間の匂いを付けないようにする
粘着シートは安全性にも注意が必要です。
ペットや小さな子どもが触れないように物理的なバリアを設けたり、粘着面に埃が溜まらないように定期的に確認しましょう。
捕獲後のネズミの回収や廃棄は、自治体のルールに従ってください。
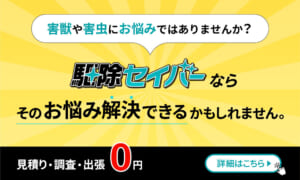
殺鼠剤の種類と選び方
粘着シートと併用して、活動が続いているエリアに殺鼠剤(ベイト剤)を設置します。
ただし、薬剤には種類があり、選び方を誤ると効果が出ないこともあるため気を付けましょう。
殺鼠剤は大きく分けて「抗凝血性殺鼠剤(第1・第2世代)」と「非抗凝血性殺鼠剤(急性タイプ)」の2タイプがあります。
| 種類 | 主な特徴 | メリット | 注意点 |
| 抗凝血性殺鼠剤(第1・第2世代) | 血を固まりにくくし、数日かけて効果を発揮する「遅効性タイプ」 | ・学習されにくく、複数個体に波及しやすい。 ・巣全体の駆除に効果的 | ・ペットや他の動物が誤食すると危険。 ・効果発現に数日かかる。 |
| 非抗凝血性殺鼠剤(急性タイプ) | 食べてすぐに効果が出る「即効性タイプ」 | ・短期間で効果が確認できる。 ・単発的な駆除に向く | ・ネズミが学習して二度と食べなくなる場合がある。 ・継続的な使用には不向き。 |
薬剤を選ぶときは、まずどんなネズミを相手にしているかを把握することが大切です。
種類によって食性や行動範囲が異なり、地域によってはスーパーラットと言われる薬剤への耐性があるネズミの場合もあります。
また、設置環境も重要です。
屋内か屋外か、食品を扱う場所かによって、使える薬剤や濃度が変わります。
どのタイプを使用する場合でも、必ずベイトステーション(専用容器)に入れて設置しましょう。
さらに、使用にあたっては以下の点も守りましょう。
- ラベル表示を厳守し、過剰な量を使わない
- 食品・調理器具と完全に隔離して保管する
- 長期使用を避け、捕獲・封鎖など他の手法とローテーションで運用する
STEP3:侵入経路の封鎖
対策をしてもネズミが再発する最大の理由は、ネズミの侵入経路が塞げていなかったというものです。
忌避剤や粘着シートでネズミ対策ができたと思っていても、ネズミが家に入ってくる道が残っていては意味がありません。
ここからは、侵入経路をしっかり断つための考え方と、プロが現場でおこなう封鎖のコツを紹介します。
「追い出す・捕まえる」だけでは不十分な理由
ネズミ駆除は「一匹を退治する」ことが目的ではなく、再び住みつかせない環境を作ることが本質です。
一時的に家の中から追い出しても、外部には常に別の個体がいて、わずかな隙間さえあればすぐに侵入してきます。
また、巣を壊された個体が戻ってきたり、他の群れが「空いた巣」に入り込むケースも珍しくありません。
つまり、「追い出す・捕まえる」だけでは一時的な効果にとどまり、構造的な対策を施さなければ再発防止は難しくなります。
長期的な効果を得るには、侵入口を一つ残らず封じる建物の防鼠化が不可欠です。
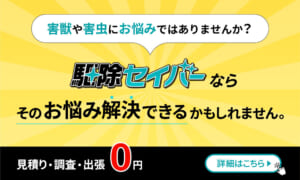
プロが使う材料とご自身で対策する際のポイント
封鎖作業の目的は、ネズミが歯でかじって突破できない強度のバリアを作ることです。
そのため、素材選びが何より重要になります。プロの現場で主に使われるのは以下のような資材です。
| 材料名 | 用途・特徴 |
| ステンレス製の細目ネット | 換気口や通風口の防護に最適 |
| パンチングメタルや金属プレート | 開口部を物理的に塞ぐ際に使用 |
| 銅メッシュ+防鼠パテ | 配管周りなど、形のイレギュラーな隙間の充填に有効 |
| ドアスイープ(隙間防止パーツ) | ドア下部の通り道を遮断するための部材 |
発泡ウレタンや柔らかい樹脂だけでの封鎖は控えてください。
ネズミは簡単にかじり破ることができ、わずか6mmの隙間でも侵入してしまいます。
そのため、6mm未満の隙間はパテや金属メッシュで充填し、より大きな開口部には金属プレートで強度を確保するのが原則です。
また封鎖の際は、以下のような場所を重点的に確認します。
- 配管や電線の貫通部
- 換気口、排気ダクト周り
- 屋根裏や破風板周り
- 床下点検口、エアコンスリーブ(配管穴)
- 戸当たりや玄関ドア下の隙間
- 基礎や壁のクラック
施工のコツとしては、素材をしっかり固定することが重要です。
リベットやビスで確実に留め、腐食しやすい箇所は防錆処理を施します。
また、防鼠対策と同時に排水や換気機能を損なわないようにする点も忘れてはいけません。
ご自身で対策をおこなう場合は、一度にすべてを完璧に封鎖しようとしなくても大丈夫です。
まずは「外から見える隙間」「ネズミの通り道に直結する部分」から優先的に対処し、難しい箇所は専門業者に依頼することがおすすめです。
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970
STEP4:痕跡をなくし、衛生環境を整える
ネズミを追い出し、捕獲し、侵入経路を封鎖したあとは、最後の仕上げとして「痕跡を消す」ようにしましょう。
ネズミの糞尿や死骸を放置すると、感染症や悪臭の原因になるだけでなく、その臭いが新たなネズミを呼び寄せてしまうこともあります。
このSTEPでは、衛生面のリスクを断ち切るための清掃・消毒作業を説明します。
感染症を防ぐ、糞尿の正しい掃除方法
ネズミの糞や尿には、レプトスピラ症やハンタウイルスなど、人に感染する危険な病原菌が含まれている場合があります。
見た目は乾いていても、細菌やウイルスは空気中に舞う可能性があるため、「乾いた状態で触れない」ことが鉄則です。
清掃の際は、まず安全装備を整えましょう。使い捨て手袋、マスク、保護メガネを着用し、肌の露出を避けます。
作業手順は以下の通りです。
- 乾拭きや掃除機の使用は避ける(菌を拡散させる恐れがある)
- 糞尿や汚染箇所を消毒液で湿らせ、数分置いてから拭き取る
- 使用したペーパーや手袋は密封袋に入れて廃棄する
- 最後に消毒剤で仕上げ拭きする
使う資材は、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤系)を適正濃度に薄めて使用します。
濃度が高すぎると素材を傷めるので、ラベルの表示濃度を厳守しましょう。
巣材や断熱材が汚染されている場合は、撤去・交換が必要です。その際には、消臭や防ダニ処理も一緒におこなうと衛生環境が安定します。
これらの作業は、素人の方が充分に行うには少々難しいです。
ご自身でのネズミ対策に不安がある場合は、無理をせず駆除セイバーにご相談ください。
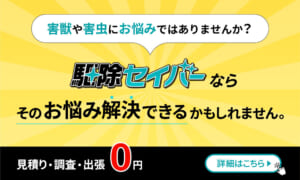
STEP5:ネズミが住みにくい環境を維持する
すべての対策を終えたあとも、環境の維持管理ができなければ再発のリスクは残ります。
ネズミは「餌・水・隠れ家」が揃った場所に戻ってきます。つまり、これらを断つことで、自然とネズミにとって住みにくい環境をつくることができます。
このSTEPでは、日常的にできる予防策(環境的防除)を徹底しましょう。
食べ物・巣の材料を与えない「環境的防除」の徹底
環境的防除は次を意識しましょう。
- 餌を与えない
- 水と隠れ家をなくす
- 定期点検を習慣化
- 家庭や職場全体でルールを共有する
ネズミ再発対策①:餌を与えない
まず基本は「餌を与えない」ことです。
食べ物は密閉容器にしまい、ペットフードなどネズミの餌になるような物を出しっぱなしにしないようにしましょう。
調理後の食べ残しやゴミはその日のうちに密封処理するのが理想です。小さなパンくずや油の飛び散りでも、ネズミにとっては立派な餌になります。
ネズミ再発対策②:水と隠れ家をなくす
次に「水と隠れ家」をなくすことが大切です。漏水している蛇口や結露は、ネズミの水源になります。
また、放置された段ボールや布、新聞紙の山は巣作りに最適な素材です。定期的に整理整頓し、屋外では草木の剪定や物置の整理をおこないましょう。
ネズミ再発対策③:定期点検を習慣化
定期点検を習慣化することが重要です。
月に一度はラットサイン(糞・かじり跡・擦れ痕)が無いかを確認し、秋口など侵入の増える季節には家の周りの隙間チェックをおこないましょう。
トラップも設置したままにせず、定期的に位置や状態を見直すとより良いです。
ネズミ再発対策④:家庭や職場全体でルールを共有する
最後に、大切なのは家庭や職場全体でルールを共有することです。
ドアや窓の開けっ放しを防ぐ、荷物の持ち込み時に検品を行うなど、日々のちょっとした注意の積み重ねが再発防止につながります。
ネズミ対策をしてるのに被害が収まらない理由
「しっかり対策しているのに、また出てきた……」
そんな声は非常に多く聞かれます。
実はネズミ対策は、単純に多くの数を駆除すれば解決するわけではなく、繁殖・耐性・侵入経路という三つの壁が存在します。
ここでは、なぜネズミ対策をしても被害が続くのか、その根本原因を解説します。
ネズミ対策より繁殖スピードが駆除を上回ってしまう
ネズミが手ごわい最大の理由は、繁殖スピードの速さにあります。
わずか数匹のメスがいれば、数か月で群れを形成してしまうことも珍しくありません。
1匹のメスは年に5〜6回出産し、1回に5〜10匹を産みます。しかも、生まれてから2〜3か月で繁殖可能になるため、驚異的なスピードで個体数が増加します。
このため、「1匹見たけど、もういなくなったから大丈夫」と放置すると、知らないうちに壁の中や天井裏で数十匹単位の群れに成長していることもあります。
ネズミ対策では、スピードがかなり重要です。
見かけた段階で、追い出し・捕獲・封鎖を同時に進める「複合対策」をおこなわないと、繁殖サイクルが途切れません。
薬剤に耐性のある「スーパーラット」が増えている
近年、都市部を中心に「スーパーラット」と呼ばれる個体が増えています。
これは、従来の抗凝血性殺鼠剤などの薬剤に耐性を持つネズミのことです。
特定の薬剤を長年使い続けることで、効き目が薄れ、薬を食べても死なない個体が生き残ります。
このような現場では、薬剤のローテーションや捕獲との併用対策が欠かせません。同じベイト剤を繰り返すのではなく、次のような対策が必要になります。
- 適応される前に別の有効成分に切り替える
- 餌の形状や匂いを変えて学習させない
- 粘着シートなど物理的手段と併用する
もし薬剤を置いても減らない場合は、種類の変更や設置方法・濃度の見直しをおこないましょう。
薬剤や毒餌が効かないと感じたら、「スーパーラット」の存在を疑うべきです。
侵入経路の特定と封鎖は素人には難しい
「ネズミがどこから入ってくるのかわからない」
これもネズミ対策後の再発原因として非常に多いパターンです。
ネズミは、6mmほどの隙間があれば体をねじ込んで侵入できます。しかし、その入口は床下や天井裏、壁の裏など、普段見えない場所にあることがほとんどです。
ご自身で見える範囲だけを塞いでも、ほとんど侵入口が塞げていないものと考えた方がいいでしょう。
また、屋根裏や配線ルートなど、高所・狭所での作業は危険を伴います。一般の方が侵入経路を完全に特定・対策するのはほぼ不可能に近いでしょう。
一方で我々プロのネズミ対策業者は、ネズミの通り道や侵入経路を可視化し専門的なネズミ対策が可能です。
その際に使用する専門機材は以下のようなものがあります。
- ファイバースコープ
- 蓄光粉・UVライト
- サーモグラフィー
加えて駆除セイバーは、ネズミ対策のノウハウや経験をもとに「ネズミが通りやすい動線」を読み解くことで、徹底した封鎖作業を可能にしています。
ネズミ対策後の再発を防ぎたいのであれば「侵入経路の封鎖精度=ネズミ対策後の再発率」と考えて、専門家の診断と施工を検討するのが最適解です。
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970
プロにしかできないネズミ対策があります
ここまで紹介した手順をすべて正しく実施できれば、多くのケースでは被害を抑えられます。
しかし、実際には「すぐに再発する」「完全に封鎖できない」と悩む人も少なくありません。
その原因の多くは、自力でおこなえる対策では限界があるというところにあります。
プロの駆除業者は、単に薬剤を使うだけでなく、建物全体の構造を読み解き、再発を防ぐための環境設計まで含めて対策をおこないます。
そのため、ネズミ対策の確実性や再発防止力が一般の方と段違いです。
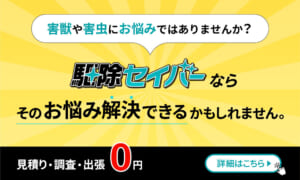
失敗しないネズミ対策業者の選び方
ネズミ対策は、どの業者に依頼するかで再発率・費用・安心感が大きく変わります。
「とりあえず安いところにしよう」と安易に決めてしまうと、ネズミ対策の質が低く、再び被害が起きるケースも少なくありません。
ここでは、信頼できるネズミ対策業者を見極めるためのチェックポイントを紹介します。
現地調査と見積もりが無料で説明がわかりやすいか
優良な駆除業者は、必ず現地調査をおこない、被害状況を正確に把握したうえで見積もりを提示します。
現場を見ずに「一律料金」「格安パック」などを提示する業者は、後から追加費用が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、「見積りに費用がかからないか」「内容を細かく説明してくれるか」もポイントです。
専門用語ばかりで説明が不十分な場合や、質問に曖昧な答えしか返ってこない場合は要注意。
信頼できる業者ほど、被害箇所の写真や図面を見せながら、対策の意図を明確に説明してくれます。
見積りは作業内容ごとの内訳を確認しよう
見積書に「ネズミ駆除 一式」とだけ書かれている場合、どこでどんな作業をおこなうのかが不明瞭で、あとから追加費用を請求されるケースがあります。
必ず、作業ごとの内訳を確認するようにしましょう。
チェックすべき主な項目は以下の通りです。
- 現地調査の有無・範囲
- 封鎖箇所の数と内容(屋内・屋外など)
- 捕獲やトラップに使う資材の種類・数量
- 清掃・消毒の有無と範囲
- 保証の範囲(期間・再発時対応の条件)
また、対策単価の根拠が明示されているかも重要です。
「なぜこの金額になるのか」を説明できる業者ほど信頼できるでしょう。さらに、施工前後の写真を提出してくれるかも確認ポイントです。
透明性の高い見積もりを出す業者は、「作業への自信」と「顧客への誠実さ」を持っている証拠です。
契約前にしっかり確認することで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
再発保証などアフターフォローは充実しているか
ネズミ対策は、「終わったあと」こそが本当のスタートです。
侵入経路の封鎖や駆除・捕獲が完了しても、外部からの再侵入や構造劣化によって、再び被害が起こることがあります。
だからこそ、ネズミ対策業者を選ぶ際は、アフターフォロー体制がどれだけ整っているかが大きな判断基準になります。
優良業者は、ネズミ対策後も定期点検や再訪を実施し、再発をゼロに近づけるためのサポートをおこないます。
ネズミ対策後に連絡が取れなくなりそうな業者は避けるようにしましょう。
保証期間と保証内容を事前にチェック
契約前に、必ず保証の内容と条件を確認しておきましょう。同じ「再発保証付き」といっても、実際にはカバー範囲が大きく異なります。
チェックすべきポイントは次の通りです。
| 項目 | 確認内容 |
| 保証対象 | 侵入・目撃・糞の再発など、どの状態を保証対象とするか |
| 無償対応の条件 | どのような場合に再施工や点検が無料でおこなわれるのか |
| 保証期間と回数 | 数か月〜1年など、期間の長さと対応回数を確認 ※駆除セイバーの場合は最長15年保証です |
| 緊急駆け付け体制 | 再発時にどのくらいのスピードで対応してもらえるか |
特に、「再発保証」と「無料対応保証」は別物であることが多い点に注意しましょう。
たとえば、「1年間の再発保証」と記載があっても、実際には「点検のみ無料」「再封鎖は有償」といった制限があるケースもあります。
保証内容をきちんと説明できるかどうかは、その業者の誠実さと施工品質を見極める重要な指標になります。
実績と専門性が確認できるか
業者選びで最も信頼性を左右するのが、経験値と専門性です。どれだけ広告が派手でも、施工の質は現場実績に表れます。
過去にどんな建物で、どんな手法で問題を解決してきたか。これを具体的に示せるかどうかが判断材料になります。
優良誤認表示や誇大広告に気を付けよう
ネズミ駆除業者の中には、見た人が勘違いするようなオーバーな表現をしている企業があるので気を付けましょう。
例えば、「100%完全駆除を保証します」「お客様満足度No.1」といった根拠のない強調や煽り文句を使う業者は要注意です。
これらは景品表示法に違反する可能性があるので、このような表現をしている企業は、ネズミ対策の質やお客様にお伝えする内容の信ぴょう性が低いので注意してください。
※No.1表記について、調査媒体の調査をもとに掲載している場合もあります。根拠がありそうかどうかを判断すると良いでしょう。
ネズミ対策に関するよくある質問
ここでは、実際にご相談が多い「市販グッズの効果」「作業時間や近隣配慮」「死骸の処理方法」について、プロの視点からわかりやすくお答えします。
すでに被害に悩んでいる方だけでなく、これから対策を始めたい方にも役立つ内容です。
Q1. 市販のグッズで効果的なのはどれですか?
市販のグッズでも、正しい組み合わせと使い方をすれば一定の効果を期待できます。ただし、被害の程度によって選ぶべき道具と対策の順序が変わります。
被害が軽度の場合は、粘着シート+ベイトステーション(毒餌箱)+隙間封鎖の組み合わせがおすすめです。短期間で通路を塞ぎ、個体数を抑えられます。
一方、活動が広範囲に及ぶ中度以上のケースでは、封鎖を前提に、広範囲でトラップを展開しつつ薬剤をローテーションで使用する必要があります。
同じ種類の殺鼠剤を長期使用すると耐性がつくため、定期的な切り替えが効果的です。
ただし、市販品には限界があります。再侵入を防ぐには、封鎖工事を含めた専門的な対策が不可欠です。
本気でネズミ対策をしたい場合は駆除セイバーにご相談ください!
Q2. 作業時間はどのくらいかかりますか?近所に知られずに作業できますか?
作業時間は建物の構造や被害の範囲によって異なります。一般的な戸建て住宅であれば、以下の時間が目安です。
- 調査:1〜2時間
- 封鎖作業:3〜5時間
- 全体の完了まで:1〜2日程度
被害が広い場合や店舗などの場合は、点検箇所や再訪の必要性に応じて工期が伸びることもあります。
また、最近は「近所に知られずに作業してほしい」という要望も多く、多くの業者では以下のような配慮サービスをおこなっています。
- 作業員が私服で訪問(作業服・社名ロゴなし)
- 無地の車両で来訪(業者名を表示しない)
- 作業音が出るタイミングを調整し、静かな時間帯での対応
- 養生・消臭処理で施工後の臭い対策
依頼前に、「近隣への配慮は可能ですか?」と事前に確認しておくと安心です。
Q3. 駆除後の死骸はどう処理すればよいですか?
駆除後に発見されたネズミの死骸は、感染症防止の観点から慎重に処理する必要があります。
素手で触れるのは絶対に避け、防護具を着用しましょう。手袋・マスク・保護メガネを身につけたうえで、消毒液を吹きかけてから拾い上げ、密封袋に入れて廃棄します。
廃棄の際は、自治体によってルールが異なります。可燃ごみで出せる地域もあれば、「動物死骸として別回収」になる場合もあります。必ず地域の規定に従ってください。
また、死骸が触れた床や壁などは再度消毒をおこない、二次汚染を防ぎます。屋根裏や壁の中で死んだ場合は、落下や電線ショートの危険があるため、自分で取り出さずに業者へ回収を依頼するのが安全です。
まとめ
ここまで紹介してきたように、ネズミ対策はただやるだけでは再発する可能性が高く、素人の方が完全に駆除するのは難しいです。
それでもご自身でネズミ対策がしたい方は、まずは、ご紹介したSTEP0〜STEP5の順序で対策をすることを意識しましょう。
調査→追い出し→捕獲→封鎖→清掃→環境維持という一連の流れをきちんと実践すれば、再発のリスクを大幅に減らすことができます。
| STEP0 | ネズミ対策前の準備・調査 |
| STEP1 | 家からの追い出し |
| STEP2 | ネズミの捕獲 |
| STEP3 | 侵入経路の封鎖 |
| STEP4 | 清掃・消毒・衛生環境を整える |
| STEP5 | ネズミが棲みにくい環境を維持 |
中でも特に重要なのが、侵入経路の封鎖です。
この封鎖作業がその後のネズミ再発率を左右するので、ネズミの侵入対策は徹底的に行なうことを推奨します。
見積もり無料!【駆除セイバー】がネズミのお悩みを解決します
「天井裏でカリカリ音がする」
「食べ物の袋がかじられていた」
「フンのようなものを見つけた」
このようなことがあれば、すぐにネズミ対策を始めましょう。
ただし、ご自身での対策は再発の可能性が高いため、少しでもご不安がある方は【駆除セイバー】にご相談ください。
【駆除セイバー】では、ネズミ被害にお困りの方のために、ご相談・現地調査・お見積もりをすべて無料で承っています。
まずは「今どんな状況なのか」を一緒に整理するところから始めてみませんか?
専門スタッフが現場の状況を見極め、最適な解決策をご提案いたします。