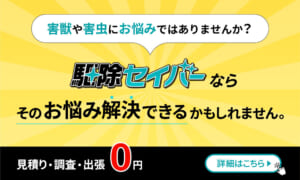ネズミ被害にご注意を!放置することで起こる危険とは
2026.01.19
「最近、夜にカリカリと音がする」 「食材の袋に小さな穴が開いていた」 そのような小さな異変を見落としていませんか? ネズミの被害は、放置すると深刻化し、取り返しがつかなくなることがあります。 ネズミ被害は早期発見と的確な対処で防げます。 この記事に出会えた今こそ、対策を始めるチャンスです! まずは自宅の状況を一緒に確認していきましょう。
CHECK
この記事を読むと以下のことがわかります。
- ネズミ被害を見逃さないためのチェック方法
- ネズミの種類と侵入経路の見つけ方
- 自分でできるネズミ被害への応急処置と、専門業者に頼るべきタイミング
ネズミ被害を放置するとどうなる?

ネズミの被害を「そのうちいなくなるだろう」とそのままにしていると、思っていた以上に深刻な事態になることがあります。
病原菌による健康被害だけでなく、家の構造や電気配線へのダメージ、さらには睡眠不足や不安感といった精神的ストレスまで広がることも。
ここでは、放置することで起こりうる具体的な危険とそのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
病原菌やアレルギー源による健康リスク
ネズミは見た目以上に危険な衛生害獣です。
人の健康を脅かすのは、直接噛みつかれることよりも、糞尿・唾液・被毛・ダニやノミなどを介した「病原体の拡散」にあります。
こうしたリスクを防ぐためには、「素手で触らない・乾拭きしない・消毒と換気」を徹底することが基本になります。
そのため、ネズミ被害を軽く考えたまま掃除や片付けをすると、かえって健康被害を拡げてしまうことがあるので気を付けてください。
ここからは、代表的な感染症や症状を具体的に見ていきましょう。
サルモネラ菌などによる食中毒
ネズミのフンや尿には次のような食中毒原因菌が含まれていることがあります。
- サルモネラ菌
- カンピロバクター菌
- 大腸菌
とくに、キッチンや食品保管場所・食器棚・ペットフードの保管容器などに侵入した場合、食品やその包装を汚染してしまう恐れがあり、非常に危険です。
たとえば、ネズミが食品袋をかじったり、その上にフンを落としたりすると、菌が包装の外側に付着します。
それに気づかずに手で触れ、食事中や調理中に口へ運んでしまいます。これが典型的な二次感染のルートです。
| サルモネラ菌 | 発熱・腹痛・下痢・吐き気などの症状が現れ、重症化すると脱水症や敗血症を引き起こすことがあります。 |
| カンピロバクター菌 | 下痢・腹痛・発熱・吐き気などの症状が現れ、まれに手足の麻痺などを引き起こすギラン・バレー症候群を発症することもあります。 |
| 大腸菌 | 激しい腹痛や水様性の下痢、血便などの症状が現れ、重症化すると急性腎不全などを引き起こす溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症することもあります。 |
予防のためには、食品は密閉容器で保管し、棚や床は定期的に消毒することが大切です。
開封後の調味料やペットフードは密閉して早めに使い切り、長期間放置された食品は思い切って廃棄するようにしましょう。
<関連記事>
これ、ネズミのフンかも?フンを見つけたら考えるべきこととは
ハンタウイルスやレプトスピラ症
ネズミの糞尿が原因で感染するウイルス・細菌もあります。
代表的なのがハンタウイルス感染症とレプトスピラ症です。
| ハンタウイルス | 乾燥したフンや尿の粒子を吸い込むことで感染し、発熱や倦怠感から始まり、重症化すると腎機能障害(腎症候性出血熱)や肺出血を引き起こすことがあります。 |
| レプトスピラ症 | 尿に含まれる病原菌が皮膚の傷口から体内に入ることで感染し、発熱・筋肉痛・黄疸などの症状を呈します。 |
こうしたリスクが問題になるのは、天井裏の掃除・倉庫の片付け・庭の物置の移動といった、普段手を入れない場所を扱う場面です。
乾拭きすると糞尿が舞い上がり、ウイルスが空気中に混じる恐れがあります。
そのため、作業時には手袋・防塵マスク・使い捨てエプロンなどを装着し、清掃の際は水で湿らせてから拭き取るようにしましょう。
また、汚染物は密封して可燃ごみに出し、作業後には必ず手洗い・うがいを行いましょう。
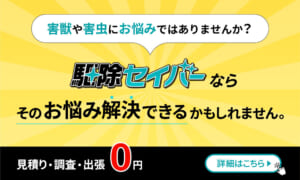
ダニ・ノミによるアレルギーや皮膚炎
ネズミの体には、ダニやノミが寄生していることがあります。
ダニやノミはネズミがいなくなった後も、寝具・カーペット・断熱材などに移動し、人やペットを刺咬する(刺す)ことも。
刺咬されると、赤い発疹・強いかゆみが出ることがあり、掻き壊すことで二次感染を引き起こすこともあり注意が必要です。
また、ネズミの巣や汚染された素材(断熱材・巣材・ホコリ)にはダニ・ノミやその糞・脱皮殻が含まれます。それらはアレルゲンとして喘息・鼻炎・アレルギー性皮膚炎の原因になることがあるので気を付けましょう。
これらのネズミ被害を予防するには
ネズミが家に棲みつくと、前述のような健康被害が発生します。
予防には、駆除後の巣材撤去・汚染部分の徹底的な消毒が必要で、寝具・カーペットは高温乾燥(60℃以上)やダニ駆除機能付き乾燥処理を行うと効果的です。
このようにネズミによる健康被害は、感染症からアレルギーまで多岐にわたり、人やペットの生活に大きな影響があるので困りものですね。
次に、健康リスクだけでなく、家そのものの安全や資産価値を損なう物理的な被害についてご説明します。
家の損壊や資産価値の低下

ネズミの被害は、健康面だけでなく、家そのものの価値や安全性にも大きな影響を与えます。
ネズミは鋭い前歯で木材や断熱材、電気配線などをかじるため、気づかないうちに住宅の内部構造を傷めてしまうのです。
天井裏や壁の中など、ふだん目に見えない場所の被害が表面化したときには、既に修繕費が高額になっているケースがあるので注意しましょう。
ここからは、ネズミが家や資産に与える具体的なダメージとその危険性をご紹介します。
柱や断熱材をかじられ、家の構造が劣化する
ネズミは常に歯が伸び続ける動物で、その歯を削るために硬いものをかじります。木の柱、合板、断熱材など、家のあらゆる部材がその対象です。
断熱材をかじられると、冬は暖房の効きが悪くなり、夏は冷気が逃げやすくなるなど、光熱費の増加にもつながります。
また、木材部分をかじられ続けると、家の構造そのものが弱くなり、長期的には耐久性の低下やカビの発生を招くおそれもあります。
一見「少しかじられただけ」に見えても、内部で巣が作られていることがあるため、早めの点検が重要です。
電気配線をかじられることによる漏電・火災リスク
もうひとつ見逃せないのが、電気系統への被害です。
ネズミは電線の被膜をかじることがあり、これが原因で漏電やショートが発生する危険があります。
東京消防庁の資料によると、平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は 97件にのぼるとされています。
壁の中や天井裏にある配線が焦げた場合、見た目では気づかず、夜間に発火することもあり大変危険です。
ブレーカーが頻繁に落ちる、壁の中から焦げ臭いにおいがする、といった異常がある場合は、自分で確認せず、必ず電気業者や害獣駆除の専門業者に相談するようにしましょう。
参考:【東京都保健医療局】ねずみが与える被害について(PDF)
家財や食品の汚損・廃棄コスト
ネズミの行動範囲は広く、家の中のさまざまなものに被害を及ぼします。
収納していた衣類や布団、段ボールの中の書類などがかじられてボロボロになるほか、フンや尿で汚染されることで衛生的に使えなくなることもあります。
また、食品を保管している棚に侵入されると、食材がかじられたり包装が破れたりして廃棄を余儀なくされます。
被害が続けば、食品の買い替えや家具・家電の処分などに意外と大きな出費がかかることも珍しくありません。
このように、ネズミ被害は家の内部構造から日常生活品に至るまで、さまざまな部分で損失をもたらします。
放置すればするほど修繕範囲が広がり、結果的に「駆除より修理のほうが高くつく」という事態にもなりかねません。
次では、こうした物理的な被害に加えて、生活の質そのものを下げてしまうストレスや心理的負担についてご紹介します。
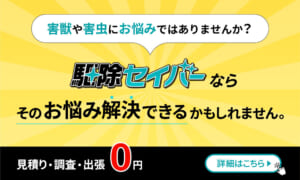
安眠を妨げ、心身をすり減らすストレス
ネズミの被害は、衛生面や建物の損傷だけでなく、心の健康にも深刻な影響を与えます。
「夜になると天井裏でカリカリ音がする」
「暗い場所で何かが動いている気がする」
こうした状況が続くと、人は無意識のうちに緊張状態が続き、睡眠不足や不安感を抱くようになります。
放置すると、心身の疲労が積み重なり、生活全体の質が下がってしまうのです。
<関連記事>
【動画あり】ネズミの鳴き声はキーキー?他の動物との見分け方
夜間の騒音による睡眠不足
ネズミは夜行性の動物で、人が寝静まったころに活発に行動します。
天井裏や壁の中から聞こえる「カリカリ」「トタトタ」という物音は、最初は小さくても、夜ごとに繰り返されると大きなストレスになります。
眠れない夜が続くことで、集中力や判断力の低下、仕事や家事への意欲減退といった影響が出ることも珍しくありません。
また、睡眠不足は免疫力の低下にもつながり、風邪をひきやすくなったり、肌荒れや倦怠感に繋がります。
「音がするのは一時的なこと」と思って放置してしまうと、ネズミが繁殖して活動範囲が広がり、さらに騒音が増える悪循環に陥ることがあります。
こうした場合、まずは音の発生源を確認し、専門業者に事前調査の依頼をおすすめします。
「家に何かがいる」という恐怖感やノイローゼ
音や影を感じながら生活することは、心理的にも負担です。
「天井の上に何かいる」「どこかに巣を作られているかも」「自宅が不衛生かも」といった恐怖や不安が頭から離れず、落ち着いて眠れなくなる人もいます。
こうしたストレスが積み重なると、家庭内の雰囲気にも悪影響を及ぼし、家族全体の心の余裕を奪ってしまうことがあります。
そのようなときは、「不安を一人で抱え込まないこと」が大切です。
早期に専門業者へ相談することで、客観的な調査と対策が進み、心理的な安心感を取り戻すことができます。
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970
ネズミが家にいるか確認する方法
「姿を見ないから大丈夫」と思っていても、ネズミは人の目につかないところで静かに動き回っています。
早期発見のカギとなるのは、ネズミが残す痕跡(ラットサイン)を見逃さないことです。
視覚・聴覚・嗅覚・そして物的な痕跡の4つの観点からチェックすれば、被害の有無をかなり正確に判断できます。
<関連記事>
家に出たのはどのネズミ?ネズミの種類を知って正しく対策
家に潜むネズミの痕跡「ラットサイン」
ラットサインとは、ネズミが通ったり住み着いたりした形跡のことです。代表的なものは次のようなものがあります。
- フン
- こすり跡
- 足跡
- かじり跡
- 物音
- 臭い
これらを総合して観察することで、ネズミの数・行動範囲・活動時間帯を推測できます。
ここからは、見逃しやすいサインを順番に確認していきましょう。
黒くて米粒のようなフンがある
ネズミのフンは、黒くて米粒くらいの長さ(6〜8mm程度)で、先がやや尖っているのが特徴です。
新しいフンはツヤがあり柔らかく、古くなると乾燥して灰色がかってきます。
フンの量が多い場所ほど、そこがネズミの通り道や餌場である可能性が高くなります。
また、フンの新旧で「今も活動しているかどうか」を判断することもできます。
ツヤのあるものがあれば、ごく最近まで動きがある証拠と考えられるため、清掃時には注意が必要です。
掃除の際は素手で触れず、濡らしてから拭き取るようにしましょう。
天井裏や壁から「カリカリ」という物音がする
夜、家の明かりを消したあとに聞こえる「カリカリ」「トタトタ」という音は、ネズミの歯をこすり合わせる音や足音であることが多いです。
活動が盛んになるのは夜10時以降〜明け方。人が寝静まる時間帯に動くため、就寝中に音で気づくケースがよくあります。
特に、音が聞こえる方向や位置にも注目しましょう。
壁の中で一定のリズムで聞こえる場合は通路として使われており、天井裏から広がるような音なら巣を作っている可能性があります。
また、昼間でも物音が続く場合は、数が増えて活動時間がずれている兆候ともいえます。
壁や柱に黒いこすり跡や小さな足跡がある
ネズミは同じ通路を何度も行き来するため、体の脂や汚れが壁や柱にこすりついて、黒っぽい筋や汚れとして残ります。
このこすり跡は、ネズミが頻繁に通るルートを示す道路標識のようなものです。
特に床から20cm前後の高さに線状の汚れが続いている場合、そのすぐ向こう側に巣や通路がある可能性があります。
また、埃の積もった場所に小さな足跡が残ることもあります。夜間にしか活動しないため、朝になってから跡を確認すると分かりやすいでしょう。
小麦粉やベビーパウダーをうっすらとまいておくと、一晩で通過した足跡がはっきり分かる場合もあります。
食品の袋や家具、配線コードに傷がある
ネズミは硬いものをかじって歯を削る習性があり、食品袋・家具の角・電気コードなどに小さな齧り跡を残します。
特にコードの被膜が剥がれている場合は、漏電や火災の原因になりかねません。
放置せず、破損部分を絶縁テープで一時的に保護し、早めにネズミの専門業者や電気工事士に点検を依頼しましょう。
また、食材の袋が破れたり、ペットフードが散らかっていたりする場合も、ネズミが餌を求めて侵入しているサインです。
被害箇所を確認し、保管場所を密閉容器に変えるなどの対策をおこなってください。
<<参考記事>>
正しいネズミ対策とは?プロが駆除について解説します!
断熱材や布きれが不自然に集められている
天井裏や押し入れの奥で、ちぎれた断熱材や布きれ、新聞紙などが団子状にまとまっている場合は、ネズミが巣を作っている可能性が高いです。
巣の周囲には必ずと言っていいほどフンや尿の跡があり、独特のアンモニア臭がします。
そこに子ネズミが生まれている場合もあるため、決して素手で触らないようにしましょう。
このような痕跡を見つけたら、すぐに業者に調査を依頼し、巣材の撤去と殺菌・消毒を行うことが大切です。
自分で処理するとアレルギーや感染症の原因になることがあるため、専門的な防除処理を推奨します。
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970
棲みついたネズミの種類はどれ?
ネズミといっても、すべてが同じではありません。日本の家屋に棲みつく代表的な種類は次の3種類です。
- クマネズミ
- ドブネズミ
- ハツカネズミ
この3種類は、それぞれ好む環境・侵入口・行動パターンが異なるため、正しく見分けることが対策の始まりになります。
たとえば、同じ駆除剤でも、種類によって効果の出やすい場所や仕掛け方が異なってきます。
天井裏が得意な「クマネズミ」

クマネズミは、細身の体と長い尻尾が特徴のネズミで、体長は15〜20cmほど。耳が大きく、乾燥した高い場所を好みます。
高所を移動するのが得意で、天井裏や壁の中、配線やパイプの上などを軽快に動き回ります。
警戒心が非常に強く、学習能力も高いため、罠や毒餌を設置しても一度警戒すると近づかなくなることもあります。
活動の痕跡としては、天井裏からの足音や、高い位置に点々と残る小さなフンが代表的です。
乾燥した家屋やマンション、ビルの上層階などに多く見られるため、都市部では最もよく発生するネズミです。
もし夜間に天井から音がする場合は、このクマネズミの可能性を疑ってみましょう。
水回りを好む大型の「ドブネズミ」

ドブネズミは、3種類の中でも体が最も大きい種類です。
体長は20〜25cmほどで、尻尾はやや短め。湿った場所を好み、下水道や水路、建物の基礎や床下などに巣を作ります。
泳ぎや掘るのが得意で、排水管の隙間や基礎の割れ目から侵入することがあります。
見た目も行動も力強く、壁や床をかじる力が強いため、被害が大きくなる傾向があります。
屋外では、家の外壁の下に小さな穴(直径3〜5cm)を掘って出入りすることが多く、泥で汚れた足跡が近くに残るのが特徴です。
また、水回りでかじられた配管や、低い場所の齧り跡が見つかった場合は、ドブネズミの仕業である可能性が高いでしょう。
戸建て住宅や飲食店の厨房、倉庫の裏など、湿気の多い環境では特に注意が必要です。
倉庫や物置に多い小型の「ハツカネズミ」

ハツカネズミは、体長6〜10cmほどの小型のネズミで、見た目は一見かわいらしくもありますが、繁殖力が高く、数が増えると一気に被害が拡大します。
穀物や種子を好み、屋外の隙間や倉庫、物置から侵入してきます。
乾燥した場所でも湿った場所でも生活できるため、郊外や農村部の家屋に多い種類です。
痕跡としては、小さくコショウ粒ほどのフンや、食品袋に残る細かいかじり跡が挙げられます。また、狭い場所に巣を作ることが多く、ダンボールや布の切れ端を集めて小さな巣を作る習性があります。
体が小さいため、5mmほどの隙間があれば簡単に入り込める点も特徴です。
ネズミはどこから侵入する?
ネズミは驚くほど狭いすき間から家に入り込みます。
体が柔らかいため、1cm程度の穴や隙間でも通り抜けられるといわれています。「どこから入ってきたのか分からない」という声が多いのもそのためです。
侵入経路を見つけて塞ぐことが、再発を防ぐうえで最も重要な対策になります。まずは屋外から見える場所を中心に、代表的な侵入口を確認してみましょう。
<関連記事>
ネズミの侵入経路はどこ?家に入られたときの対処法とは
屋外からの侵入口
ネズミは地面を走るだけでなく、壁を登り、屋根裏にまで到達します。
そのため、侵入口は「上(屋根まわり)」にも「下(基礎まわり)」にも存在します。外壁の上部から下部にかけて、よくある侵入ポイントを順にご紹介します。
屋根の隙間や壁のひび割れ、通気口
ネズミは高い場所にも難なく登ります。特に屋根瓦の浮きやズレ、軒天(のきてん)の破れなどは、家屋の上部から侵入する絶好のルートです。
また、外壁にできた小さなひび割れや、通気口の金網の目が粗い場合も注意が必要です。こうした場所は、クマネズミのような高所を好む種類にとって格好の出入り口になります。
点検する際は、脚立を使うよりも、まず地上から双眼鏡やスマートフォンのズーム機能で観察するのがおすすめです。
屋根裏から天井の隙間に風や光が漏れている場合も、外部とのつながりがあるサインといえるでしょう。
基礎部分のわずかな隙間や配管の貫通部
ドブネズミなどの大型種は、建物の下部から侵入することが多いです。
給水管やガス管などの配管まわりの立ち上がり部分には、モルタルの欠けやすき間が生じやすく、そこから床下へ入り込むケースがよくあります。
また、床下換気口の金網が破れている場合も同様に危険です。日中、家の外周をしゃがんで点検し、泥の跡や黒いこすれ跡がないか確認してみましょう。
もし見つけた場合は、金網・パテ・ステンレス製ブラシ材などでしっかりと塞ぐことで再侵入を防げます。
意外と見落としがちな侵入口
ネズミは屋外からだけでなく、家の設備まわりや普段開けない場所からも侵入します。特に見落としやすいのは、エアコンや換気設備、雨戸の戸袋といった機械や建具のすき間です。
これらは建物の機能上、完全に密閉されていない構造が多く、ネズミにとっては手軽な出入口になります。ここでは、特に注意したい3つの侵入口を紹介します。
エアコンのドレンホースや室外機周り
エアコンのドレンホース(排水ホース)は、室内機からの結露水を屋外に流すために設けられています。
しかし、このホースの先端が開いたままになっていると、ネズミがそこから入り込み、ホース内を伝って室内へ侵入することがあります。
また、エアコンの配管が通る壁の貫通スリーブまわりのすき間や、配管を隠す化粧カバーの中の空間も要注意です。
室外機の裏やカバーの内側には、ネズミが通れる程度のすき間ができやすく、見た目には気づきにくいものです。
換気扇やシャッターの隙間
換気扇の外側にあるフードは、空気を通すために開閉する構造ですが、逆止弁の機能が壊れていると常に開いた状態になります。そこからネズミが侵入し、ダクト内や壁裏に巣を作ることがあります。
また、シャッターボックスの内部も盲点です。
戸建てやガレージのシャッター上部には空洞があり、長期間使用していないと巣材が溜まり、ネズミが入り込むことがあります。
さらに注意したい点が、キッチンのレンジフードや排気フード周辺です。金属の隙間や開口部が劣化して広がることがあり、そこから屋内に侵入するケースも見られます。
換気扇やレンジフードの外側は、定期的に風の通りや金網の破損をチェックしておくとよいでしょう。
長期間開けていない雨戸の戸袋
意外に多いのが、雨戸の戸袋(とぶくろ)からの侵入です。
長期間開けていない戸袋の内部には、落ち葉やホコリ、断熱材の切れ端などがたまり、ネズミが巣を作りやすい環境になります。
また、戸袋の底部にある排水穴の広がりや、経年でできたすき間から出入りする点も注意です。
もし雨戸の開閉時にガサガサという音がしたり、内部からゴミが落ちてきたりする場合は、ネズミが潜んでいる可能性があります。
掃除する際は、掃除機で吸い込むのは避け、防塵マスクと手袋を着用のうえ、慎重に取り除きましょう。
被害を食い止めるための対策
ネズミの被害は、放置すればするほど拡大します。ただし、すぐに専門業者を呼べない場合でも、応急処置としてできることはいくつかあります。
ここでは、家庭で行える追い出し・捕獲方法と、その際に注意すべき点を解説します。
自分でできる応急処置
一時的な対策としては、「追い出す」「捕まえる」「再発を防ぐ」という3つの視点が基本です。
ただし、どの方法も効果には限りがあり、長期間放置したり誤った使い方をしたりするとリスクが伴います。
安全を確保しながら、被害拡大を防ぐための応急手段を見ていきましょう。
忌避剤や超音波で追い出す
ネズミは嗅覚や聴覚が敏感なため、強い臭いや特定の周波数を嫌います。
市販の忌避スプレーやくん煙タイプの薬剤、超音波装置を使えば、一時的にネズミを追い出すことが可能です。
効果が出やすい設置場所は、ネズミが通りやすい壁沿い・天井裏・流し台の下など、暗くて暖かい場所です。
ただし、これらの方法は、ネズミが慣れたり避けたりするため、長期間使い続けても効果が薄れてしまいます。
数日から1週間を目安に場所を変えたり、種類の異なる製品を併用したりしましょう。
また、使用時は安全面にも注意が必要です。小さな子どもやペットがいる家庭では、誤って触れたり吸い込んだりしないよう、設置場所を工夫してください。
粘着シートや罠で捕獲する
ネズミの通り道が特定できている場合は、粘着シートやバネ式の罠を使って捕獲する方法もあります。
設置する場所は、ネズミが壁伝いに移動する習性を利用して、壁沿いや狭い通路に複数枚並べるのが効果的です。手のにおいを嫌うため、設置時には手袋を着用して作業しましょう。
捕獲後は、衛生面に十分注意が必要です。粘着シートにかかったネズミは素手で触らず、ビニール袋に密封して処分します。
使用したシートや周囲の床面はアルコールや次亜塩素酸などで消毒し、感染を防ぐようにしてください。
また、屋外で設置する場合は、ペットや野生動物が誤ってかからないよう箱型トラップやカバー付きの粘着板を使うと安全性が高まります。
自力対策による再発の可能性と安全性の問題
応急処置で姿が見えなくなっても、根本原因である侵入口が残っていれば再発します。
ネズミはわずかな隙間を見つけて何度でも戻ってくるため、封鎖作業まで行わないと完全な解決にはなりません。
また、天井裏や配線まわりでの作業は転落や感電の危険があり、薬剤を誤って使うと中毒や火災のリスクもあります。
特に毒餌は、ネズミ以外の動物や小さな子どもが誤って食べると非常に危険です。
こうした理由から、応急処置だけで被害を完全に止めるのは難しく、安全かつ根本的に解決するには、専門業者の調査と封鎖作業が欠かせません。
次では、プロに依頼することで何が違うのか、安心できる駆除の進め方をご紹介します。
根本解決をするなら専門業者への相談がベスト
ネズミの被害を確実に止めるには、「侵入口の封鎖」と「清掃・消毒」までを一貫して行うことが欠かせません。
しかし、これらのネズミ駆除を個人で完全に行うのは難しく、見落としや誤った処置によって再発するケースが多く見られます。
そこで、プロのネズミ駆除業者に相談すれば、調査から封鎖、再発防止までを安全かつ効率的に進めることができます。
ここでは、プロの作業がどのように違うのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
プロはここが違う!徹底した侵入経路の特定と封鎖
専門業者が最初に行うのは、「発生源の特定」から始まる徹底調査です。
現場では、フン・足跡・こすり跡・かじり跡などのラットサインをもとに、ネズミの通り道や巣の位置、侵入口のルートを詳細に把握します。
この調査結果に基づき、被害状況に合わせた封鎖計画を立てます。
封鎖に使用する素材も、現場の環境に応じて選定されます。
たとえば、通気を必要とする箇所にはステンレス製の金網を、湿気の多い床下には腐食しにくいパテ材を使用するなど、建物構造とネズミの習性の両方を考慮した施工がおこなわれます。
作業後には、調査写真や施工前後の報告書が提供される場合も多く、「どこを塞いだのか」「どのように再発防止を行ったのか」が視覚的に確認できます。
この見える化によって、施工後も安心して生活できる点がプロの大きな強みです。
安全な薬剤の使用と、被害箇所の清掃・殺菌消毒
専門業者による駆除では、人やペットへの安全性に配慮した薬剤を使用します。
毒餌を無差別に置くのではなく、被害範囲・ネズミの種類・建物環境を踏まえて、最も効果的かつ安全な方法を選びます。
さらに、駆除後は必ず巣材・フンの除去、殺菌・消臭作業を行います。これは衛生面の改善だけでなく、ネズミが残したにおいを取り除き、他の個体を寄せつけないための再発防止にもつながります。
作業後には、再侵入を監視するためのモニタリングや定期点検を行う業者もあり、再発時の保証制度を設けているところもあります。
「駆除して終わり」ではなく、被害の痕跡をきちんと取り除き、再発までしっかり防ぐことがプロの役割です。
ネズミ被害のよくある疑問をプロが解決します
ネズミの被害に遭うと、「これって誰の責任?」「どこまで対応すべき?」といった疑問が次々に湧いてくるものです。
ここでは、実際に多く寄せられる質問を、現場経験のある専門業者の視点で分かりやすく解説します。
Q1. 賃貸で被害にあった場合、責任と費用は誰が負うのですか?
ネズミ被害の原因が建物そのものの問題か、居住者の生活状況によるものかで、対応の主体が変わります。
一般的には、次のようになります。
| 被害の原因 | 主な内容 | 対応・費用負担の傾向 |
| 建物起因 | 構造的な隙間・老朽化・外壁や配管の劣化など | 貸主または管理会社が修繕・駆除対応を行うケースが多い |
| 居住状況起因 | 部屋ゴミの放置・部屋の清掃不足・食品の保管不備など | 借主側の責任・費用負担となる可能性がある |
まずは、管理会社や大家さんに連絡し、現地確認を依頼しましょう。 そのうえで、契約書に記載されている「特約」や「ハウスルール」に従って、費用負担の範囲が決まるのが一般的です。
トラブルを防ぐためには以下のようなものを残しておくとよいでしょう。
- フンや損傷箇所などの被害写真
- 日付の分かる記録メモ
- 業者見積書の写し
なお、最終的な判断は契約内容と管理方針によって異なるので注意しましょう。
Q2.1匹見つけたら、家には何匹くらいいると考えればよいですか?
ネズミは単独で行動することもありますが、1匹見つかった時点で複数が生息している可能性が高いと考えましょう。その理由は、繁殖力と行動範囲にあります。
たとえばクマネズミの場合、1回の出産で5〜10匹前後の子を産み、年に数回繁殖します。また、同じ通り道を共有するため、巣が1か所でも複数の個体が行き来しているケースが少なくありません。
ただし、種類・季節・巣の有無によって生息数は大きく変わるため、「何匹いる」と断定するのは難しいのが実情です。そのため、「見かけた=複数いる前提」で行動するのが安全です。
取るべき行動は、次の4ステップを参考にしてください。
- 痕跡の確認(フン・音・齧り跡など)
- 侵入口の特定と封鎖
- 捕獲・追い出し
- 被害箇所の清掃・消毒
1匹だけ駆除しても、侵入口が残っていればまた発生します。早めに家全体を確認することが、被害を最小限に抑えるポイントです。
Q3. ネズミが原因の火災や修繕に、火災保険は使えますか?
火災保険で補償されるかどうかは、被害の内容と原因の扱いによって異なります。
一般的にはつぎのようになることが多いです。
| 被害内容 | 状況の例 | 補償の可能性 |
| 配線の損傷による偶発的な火災 | ネズミが電気配線をかじった結果、ショートして火災が発生した場合 | 補償対象になる可能性がある(偶発的損害として扱われることが多い) |
| 糞尿・汚損・清掃・修繕のみの被害 | フンや尿による汚れ・壁や家具の破損など | 補償対象外である場合が多い(害獣被害は補償範囲外のことが多い) |
また、申請時には、以下の書類が求められることがあります。
- 被害箇所の写真
- 業者による原因調査報告書
- 見積書や被害品リスト
まずは安全を確保したうえで、できるだけ早く保険会社へ連絡し、担当者の指示に従いましょう。
補償内容は契約している保険約款や特約条件によって異なるため、必ずご自身の契約を確認することが大切です。
ネズミの被害に気がついたら【駆除セイバー】にご相談ください!
ネズミのフンや不審な物音、配線のかじり跡などを発見したとき、「自分で対処できるかどうか」が悩ましいところです。
ただ、応急処置だけでは安全性や再発防止までカバーできない可能性もあります。
そんなときこそ、私たち【駆除セイバー】にご相談ください。
ご相談は無料で、まずは「今の状況を一緒に整理する」ことから始められます。
【駆除セイバーの信頼できる特徴】
| 特徴 | 内容 |
| 豊富な実績 | ネズミだけでなくイタチやコウモリなどの実績も多数 |
| 経験あるスタッフ体制 | 駆除歴10年以上のスタッフが対応する体制 |
| 無料調査・見積り | 現地での調査および見積もりが無料 |
| 安全性と保証 | 損害保険や協会に加盟済みで、万が一の場合も安心 |
| 女性スタッフ対応可能 | 女性の一人暮らしなどでも安心できるよう配慮 |
ネズミの被害は、早期発見と早めの対応が、被害の拡大を防ぐポイントです。
駆除セイバーでは、ご相談・現地調査・見積もりはすべて無料です。まずは気になる点をお聞かせいただくだけでも結構です。
安全・安心を最優先に、あなたの住まいの環境改善をお手伝いいたします。
お電話はこちらからどうぞ
0120-597-970